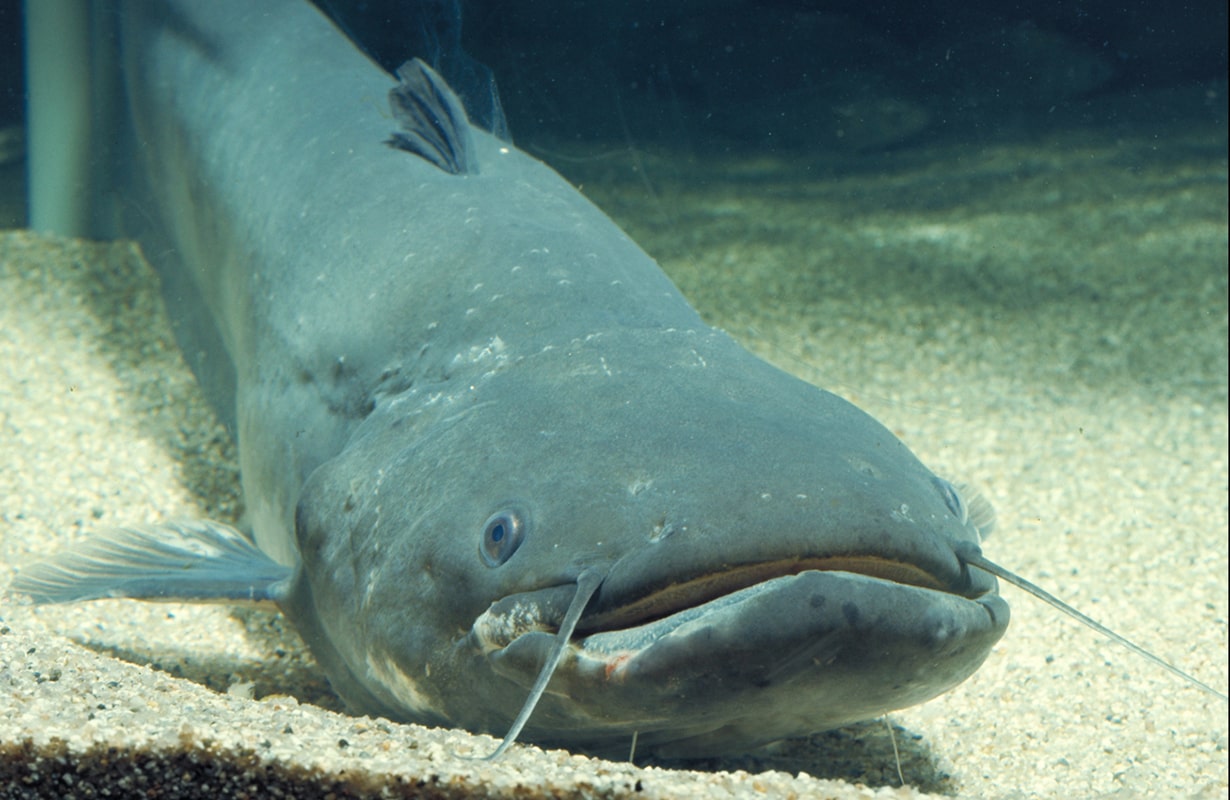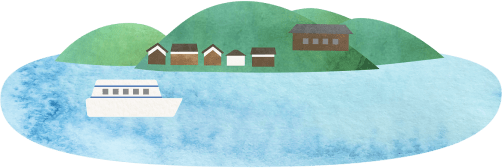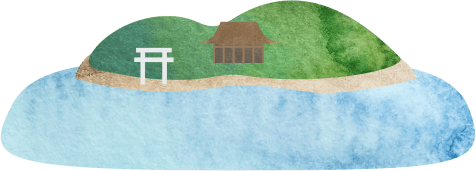琵琶湖の始まりは、現在の三重県伊賀市あたりに、約400万年前にできた大山田湖であるとされています(C)。しかし最近の研究で、大山田湖は、伊勢湾周辺にあった東海湖とひとつながりの水系だったようで、湖としても一体であった可能性が指摘されています。
東海湖がどのような湖だったのかはよくわかっていませんが、大山田湖よりは古くからあったようですので、少なくとも400万年前よりは古い時代までさかのぼるようです(D)。
その後、古琵琶湖は消長をくり返しながら北上し、約180万年前には現在の琵琶湖の南部付近に湖があったようです(B)。そして約43万年前に急速に北に広がって、現在の北湖ができました(A)。この当時の北湖は現在よりも細長く、現在の琵琶湖の形とは大きく違っていたようです。
このように視点を変えると、琵琶湖がいつできたかの答えも変わってきます。これからの研究の進展によっては、さらに違う答えが見えてくるかもしれません。